TEACHER 教員紹介

日本語・日本文学
朴 秀娟准教授
人生に寄り添ってくれる書物との出会いを

欧米の文化と歴史
佐藤 園子専任講師
ジェンダーの視点から物語を読み解く
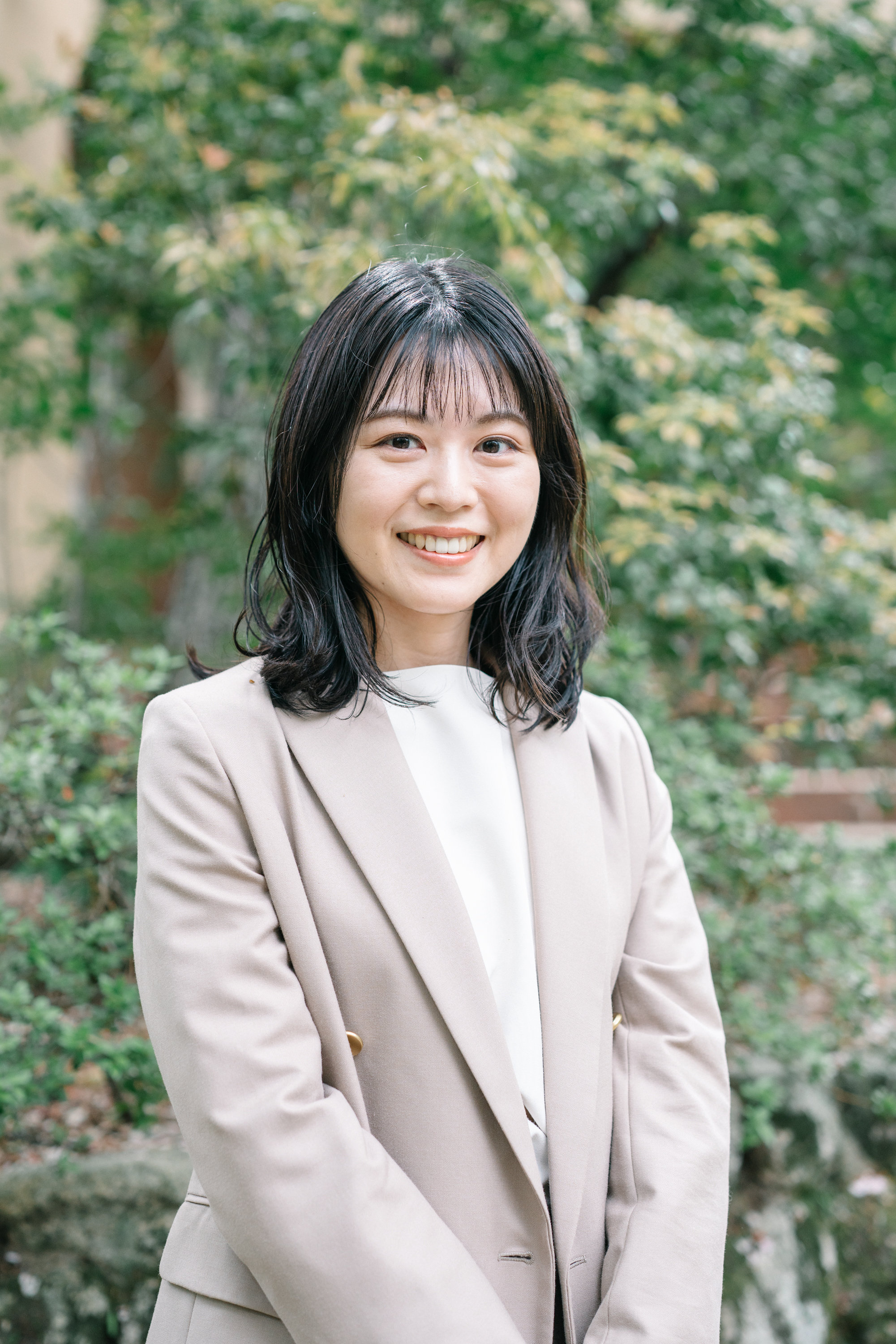
日本語・日本文学
田村 美由紀専任講師
法から社会を見るか?社会から法を見るか?

経済学・法学・国際関係論
米田眞澄教授
聖書の言葉の世界の探求

宗教学
大澤香准教授
31音のことばに託された世界をひらく

日本語・日本文学
藏中さやか教授
人間や社会を「深く」知るには、宗教学!

宗教学
中野敬一教授
インドの民主主義から「しなやかさ」を学ぶ
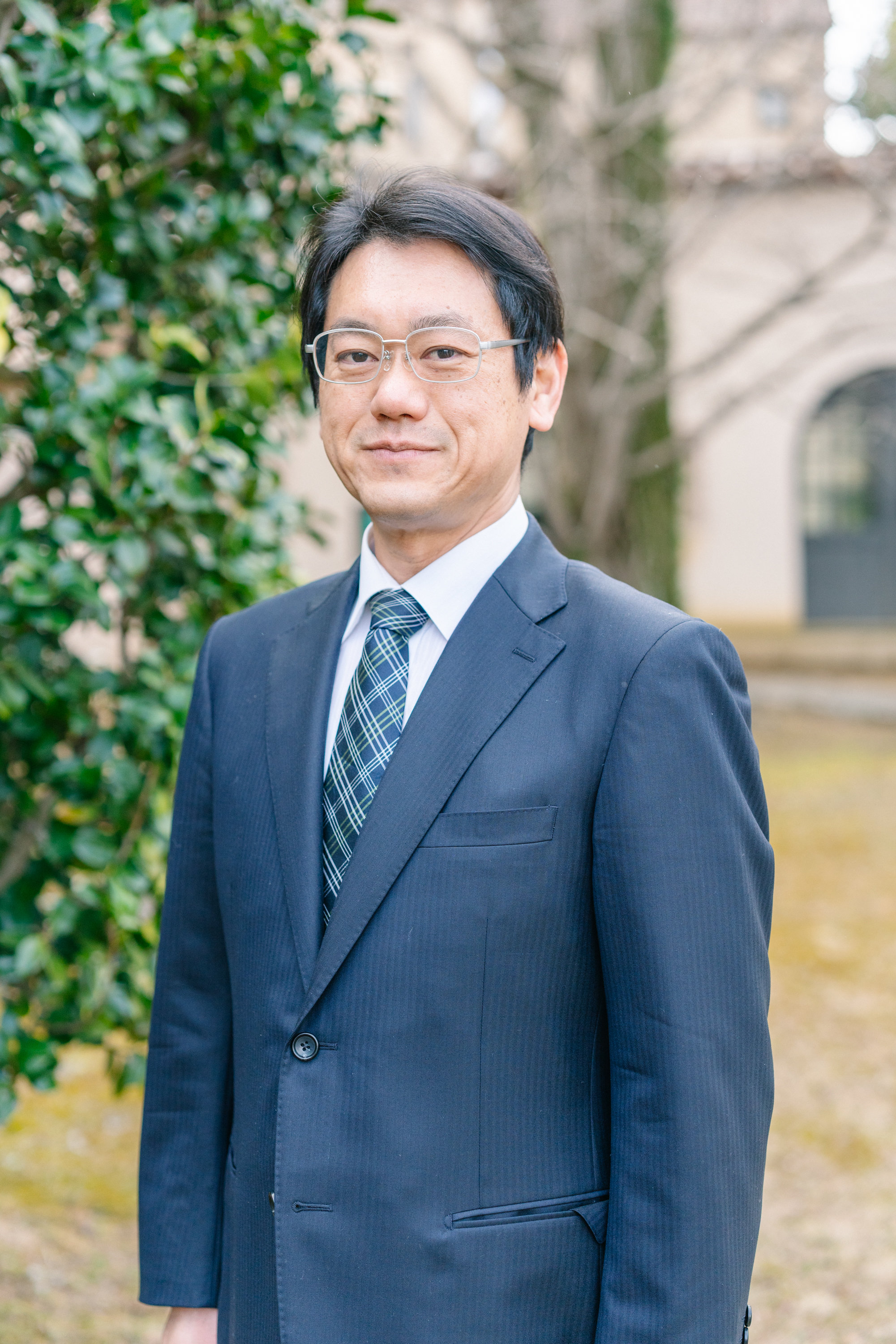
経済学・法学・国際関係論
北川将之教授
哲学とは「生きる」ことを「学び直す」こと

哲学・倫理学・美学
川瀬雅也教授
社会の論理を読み解き、常識を相対化する
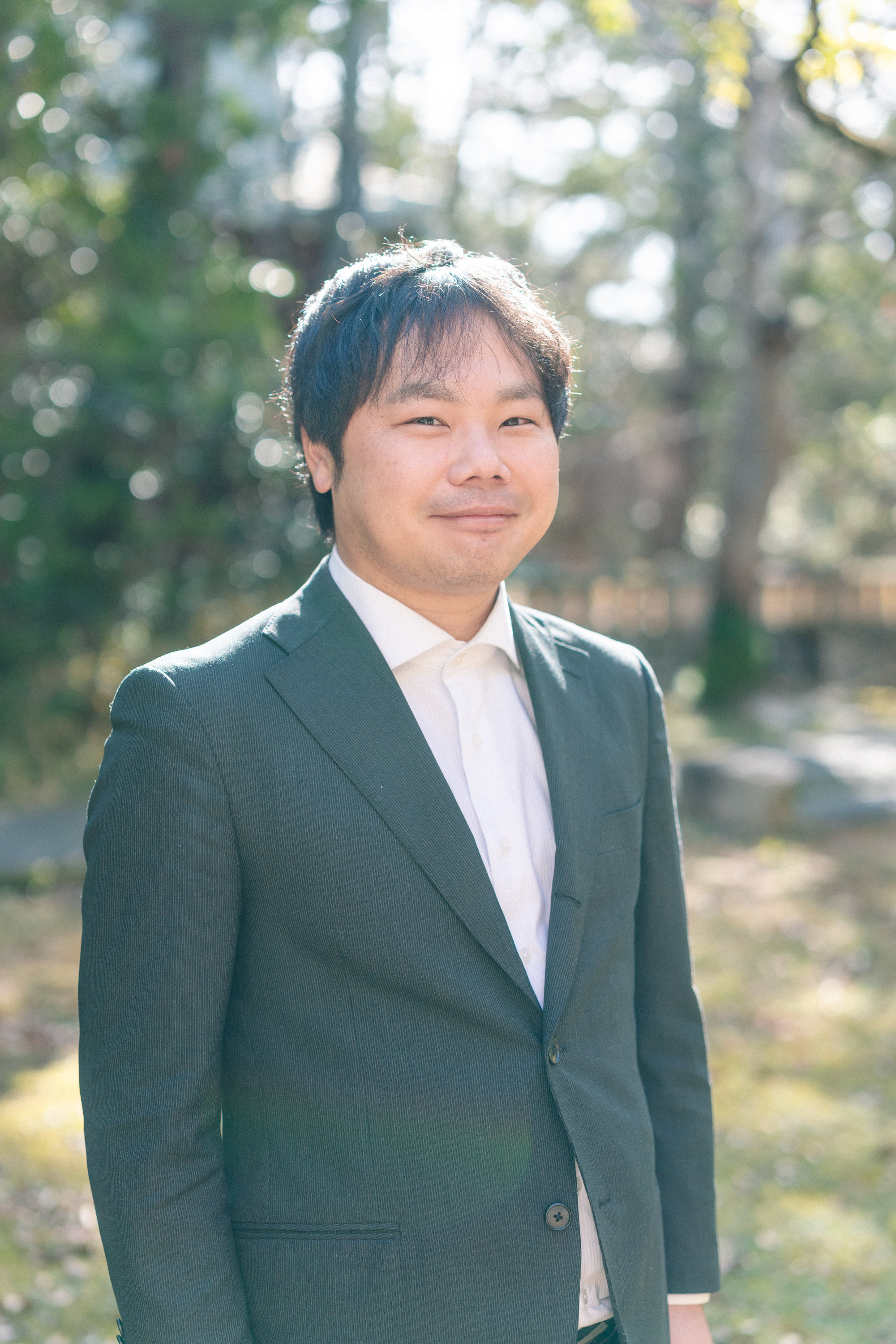
社会学・メディア
藤岡達磨准教授
本当の豊かさとは何か~環境と地域から考える
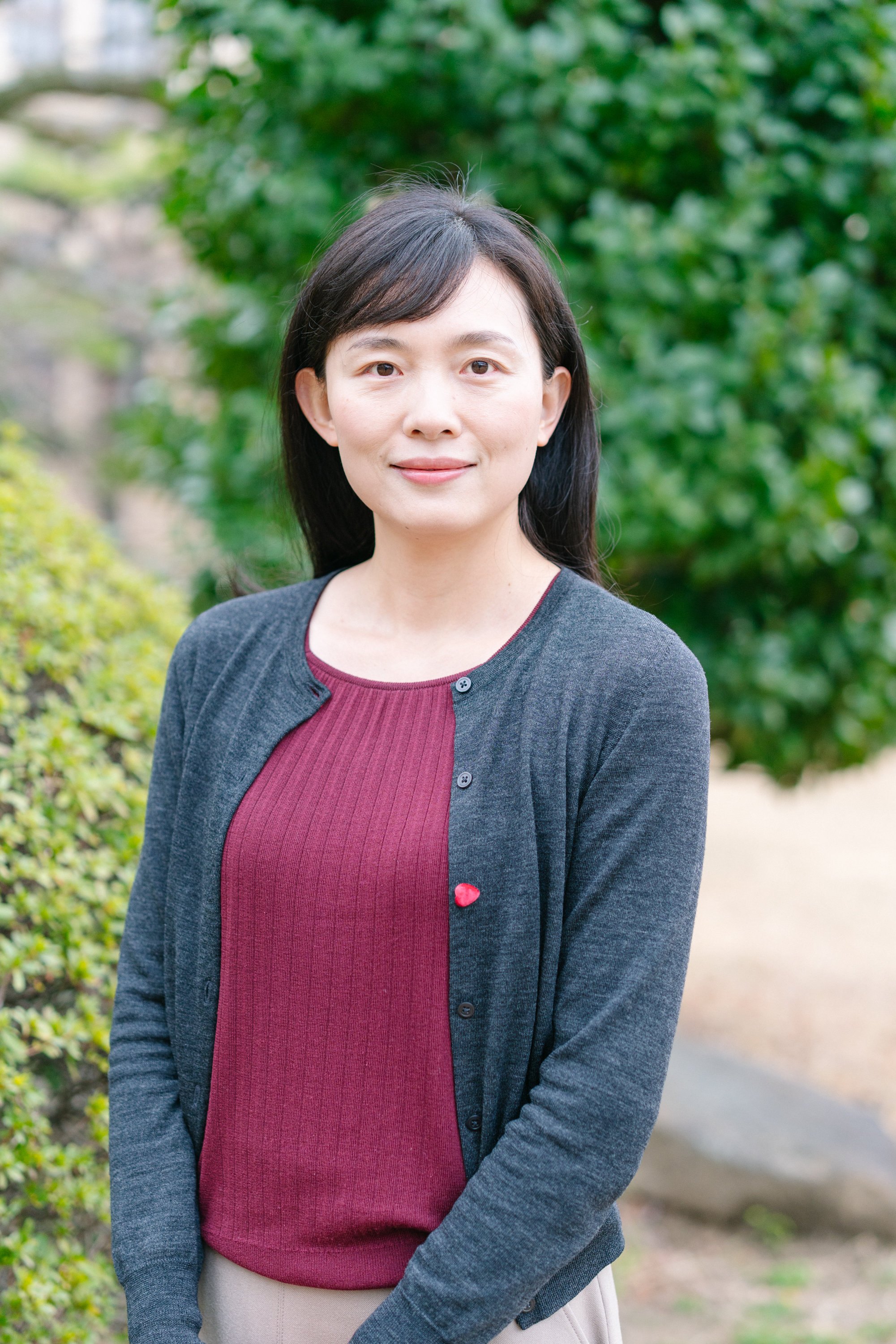
経済学・法学・国際関係論
傅喆准教授
社会は謎に満ちている
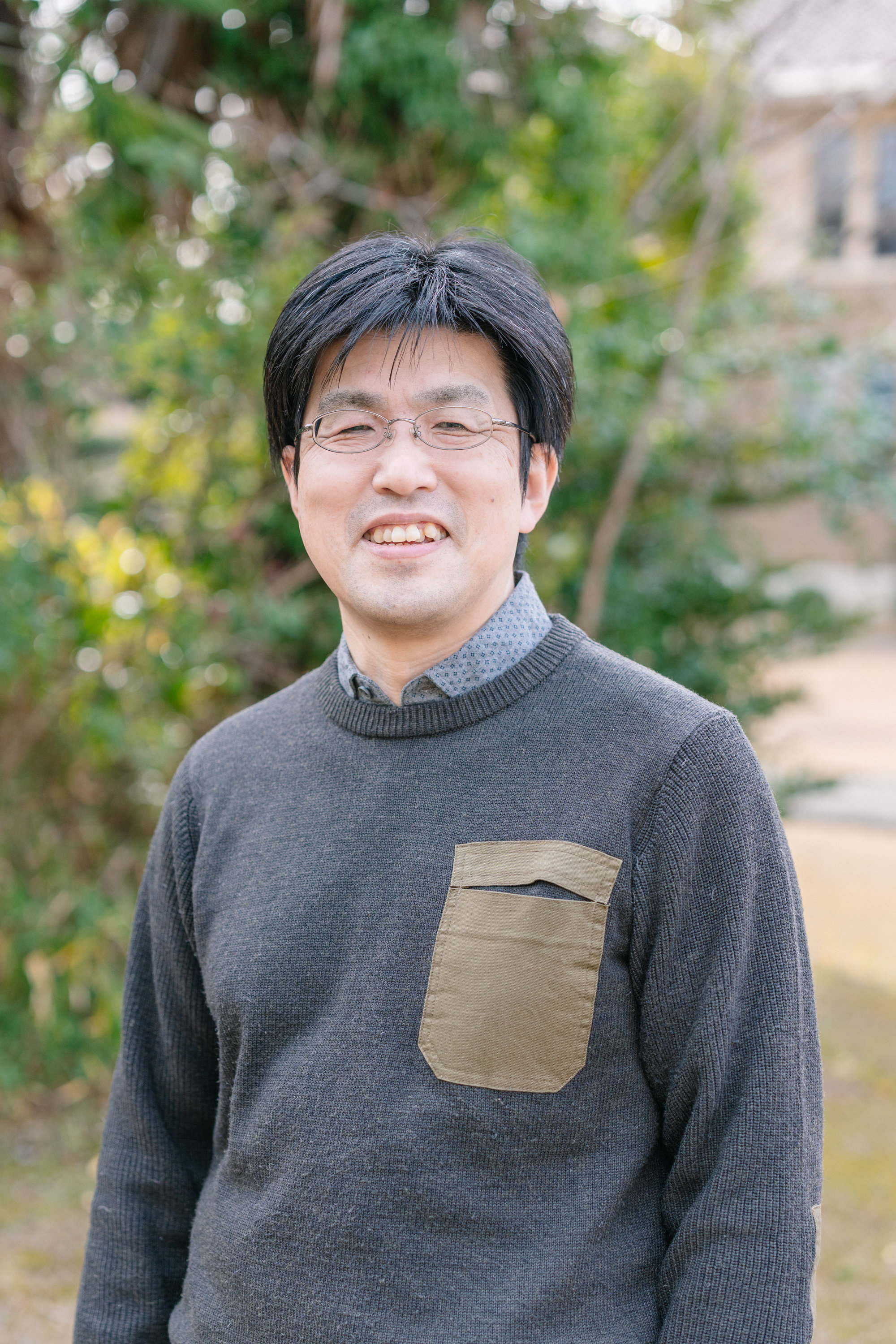
社会学・メディア
清水学教授
社会の人々の幸福な生活を実現するために

社会福祉・子ども
金田知子教授
絶学無憂

日本・アジアの文化と歴史
小林隆道教授
人はなぜ芸術を欲するのかを尋ねてみよう

哲学・倫理学・美学
三木順子教授
文学から読み解く 心と社会と今

欧米の文化と歴史
三杉圭子教授
日本語の中にある「隠れた」ルールを見つける!

日本語・日本文学
建石始教授
家族らしさをやりとりから考える

社会学・メディア
戸江哲理准教授
学ぶことは自由への扉をつくること

社会学・メディア
景山佳代子教授
教科書に現れない女性の姿を明らかにしたい
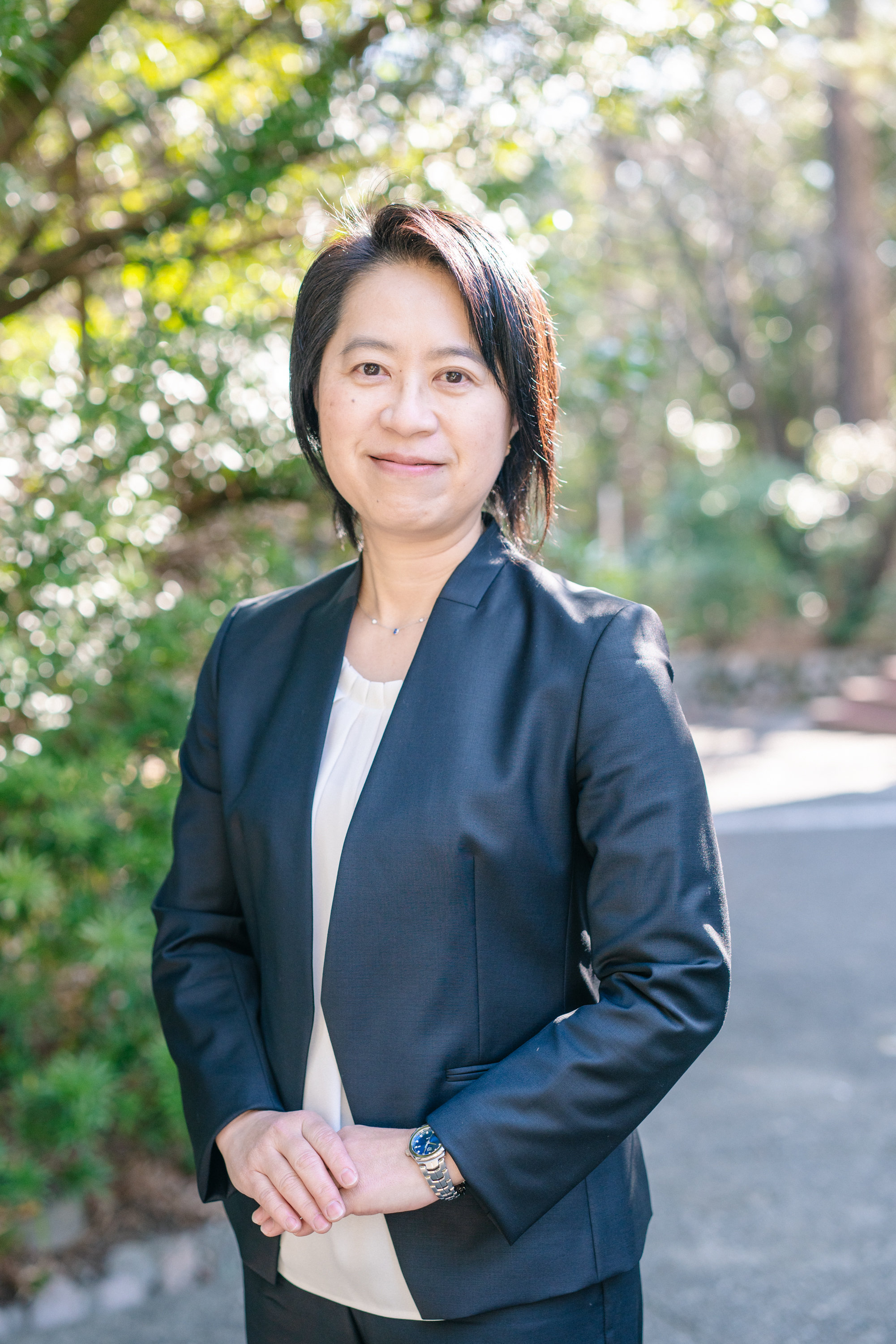
日本・アジアの文化と歴史
栗山圭子教授
過去のヨーロッパから現代の仕組みを見よう

欧米の文化と歴史
桐生裕子教授
人が抱える生活課題の解決に向けた支援
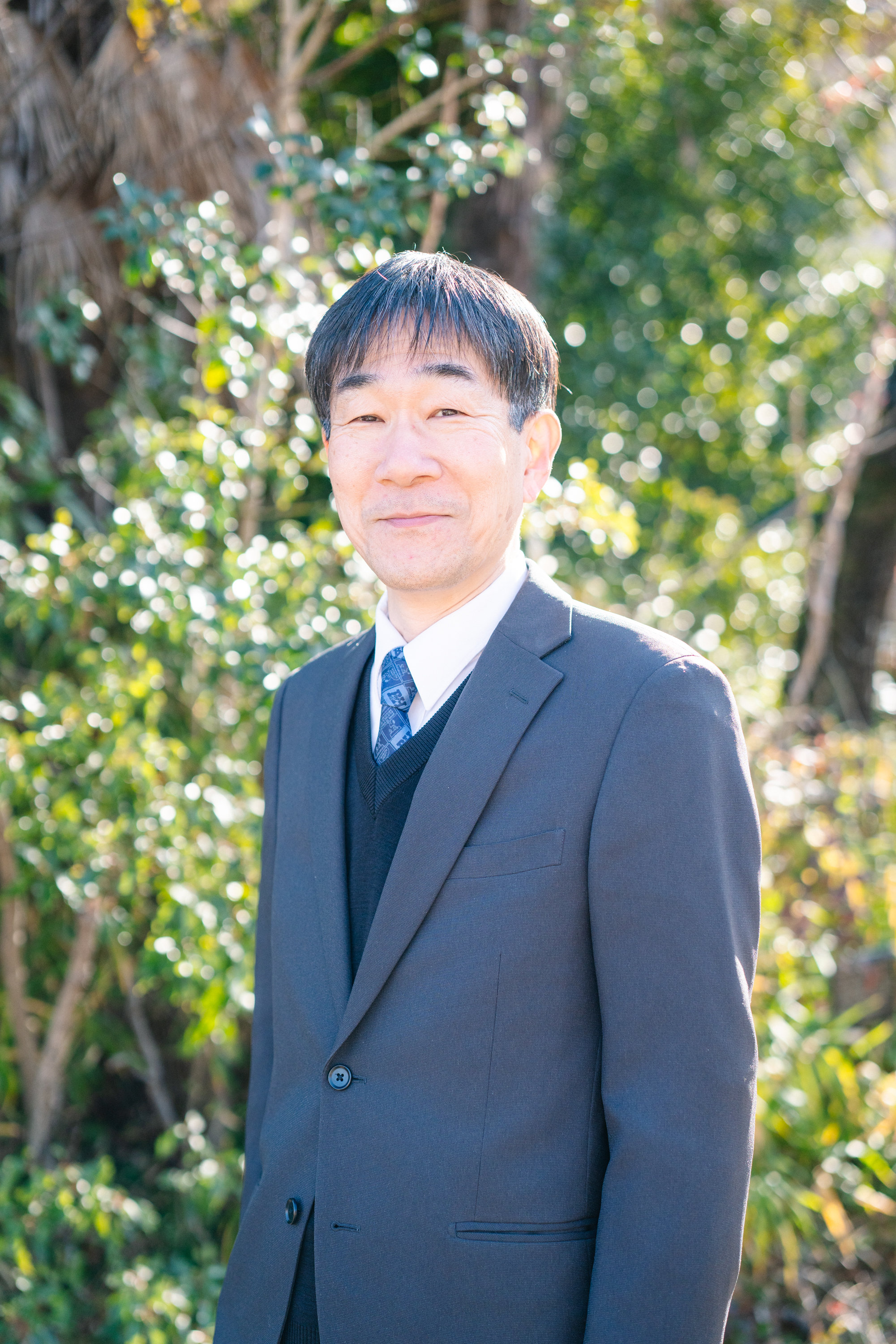
社会福祉・子ども
岩間文雄教授
学びは、人生のあらゆる場面で起動する

社会福祉・子ども
奥野 佐矢子教授
「近代」の限界を私たちは突破できるか?

日本・アジアの文化と歴史
河島 真教授



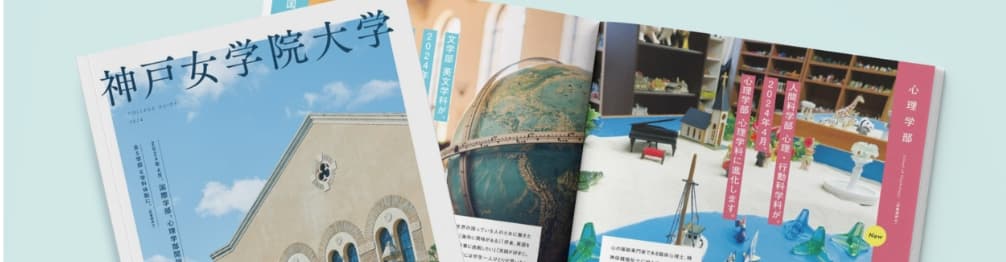



日本語を外国語として学ぶとは?